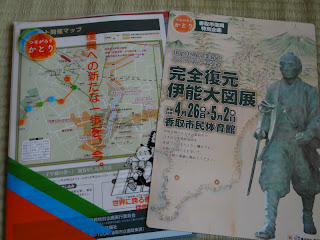私が学生の頃、就職活動等で「実施設計を行う会社」ということが、いまいちよくわかりませんでした。
学生の頃、オープンデスクでお世話になりました都内の研究所(コンサル)においては、どちらかというと調査や計画(もちろん設計もありましたが)、大学で学んできたことに近い感じがして、都市や生活環境の設計を行う会社はこれらのコンサルと同じようなのかなとも思っていたりもしました。
建築分野では、実際に詳細の図面(意匠、構造、設備)を設計事務所やハウスメーカーなどでやるのだろうとも無知ながらに感じておりましたが、都市計画やまちづくり、空間デザイン分野での、コンサルで行う実施設計についてはどんな感じなのかはよくわからなかった...。
設計・計画に携わってる者から見て、公園や都市、地域空間についてや 北関東でのランドスケープデザイン・造園外構設計の現状、身のまわりの出来事から思ったこと、日常の話題など気持ちまで含めてざっくばらんにレポート、つぶやいていきます。
(都市部より未熟な点もあれば、その逆もある。)
【東北芸工大 環境D 3期生のいま】
同期の仲間たちはそれぞれ、建築や都市計画の分野で活躍していますが、地方ですとこんな感じです。中央でしかできないこと、地方でしかできないこと、いろいろあります。
自分の周りの出来ごとを中心に、肌で感じたものごと 笑いや感動したこと 思ったこと あるときは苦悩の日々を。 ちぐはぐな文章は愛嬌ということでm(_ _)m
仕事をしていく上で、プランニングの仕事においては気持ちの部分も内容に大きく影響します。創造性のある仕事を「純粋にやっていくため」には大切な要素であると思いますので。
2012年6月10日日曜日
2012年6月8日金曜日
地域の風景 那須芦野地区
那須町芦野の田園風景。
ここの風景はなんだか懐かしく、私が昔学生のときに研究の一環で訪問いたしました山形県の大石田町や北村山地方の風景とも似たような印象を受けました。
そして、田園風景については、自分の育った千葉県香取市とも似たようなところがある感じもして...。
往時の集落(まちなみ)の骨格が残っている芦野地区。
ここの風景はなんだか懐かしく、私が昔学生のときに研究の一環で訪問いたしました山形県の大石田町や北村山地方の風景とも似たような印象を受けました。
そして、田園風景については、自分の育った千葉県香取市とも似たようなところがある感じもして...。
往時の集落(まちなみ)の骨格が残っている芦野地区。
2012年6月2日土曜日
学生時代を振り返っての講評
先日(5/30)のこと、母校学生さんのランドスケイプデザイン課題を講評する貴重な機会をいただくことができました。
その中で、学生さんの課題作品を見ながら、自分の学生時代のこと、実際の仕事のこと、どのようにアドバイスしたらよいかなど、恥ずかしながら頭の中にいろんな思考が右往左往するような状況でもありましたが、何かのきっかけになればと思いまして、講評をさせていただきました。
結果としては、自分の伝えたかったことの全てはお話することが出来ませんでしたが、大筋が伝わってくれていたら幸い だと思います。
(当日の補足として以下に記載いたします。どちらかというと、技術的内容というよりは今後の課題作成等への手法、考え方として...)
実際の設計などの仕事に置き換えてみると、調査→課題抽出→計画→設計→発表 という一通りの流れについて、それぞれのパート部分がしっかりしている必要があります。
実際の設計コンペや設計プロポーザル方式では、さまざまなしがらみがあるにしろ、それぞれの部分がしっかりし、どれかひとつがかけてしまった場合は、減点の対象となり尾を引いてしまう(落選する)ことが多々あるのです。
その中で、学生さんの課題作品を見ながら、自分の学生時代のこと、実際の仕事のこと、どのようにアドバイスしたらよいかなど、恥ずかしながら頭の中にいろんな思考が右往左往するような状況でもありましたが、何かのきっかけになればと思いまして、講評をさせていただきました。
 |
| 大学裏の棚田風景を改めてみてみる |
結果としては、自分の伝えたかったことの全てはお話することが出来ませんでしたが、大筋が伝わってくれていたら幸い だと思います。
(当日の補足として以下に記載いたします。どちらかというと、技術的内容というよりは今後の課題作成等への手法、考え方として...)
実際の設計などの仕事に置き換えてみると、調査→課題抽出→計画→設計→発表 という一通りの流れについて、それぞれのパート部分がしっかりしている必要があります。
実際の設計コンペや設計プロポーザル方式では、さまざまなしがらみがあるにしろ、それぞれの部分がしっかりし、どれかひとつがかけてしまった場合は、減点の対象となり尾を引いてしまう(落選する)ことが多々あるのです。
2012年5月21日月曜日
2012年5月20日日曜日
小江戸 栃木のまちなみ
関東の三大小江戸といえば、「佐原、川越、栃木」
先日は、地元香取市の佐原のまちなみについて触れましたが、今回は栃木県の南部に位置する栃木市について触れることとします。
栃木市は、蔵のまちとしても有名で、風情あるまちなみが残っております。
今回は丁度、シネマイベント(5/19~20)とも重なったこともあり、賑わいをみせておりました。
先日は、地元香取市の佐原のまちなみについて触れましたが、今回は栃木県の南部に位置する栃木市について触れることとします。
栃木市は、蔵のまちとしても有名で、風情あるまちなみが残っております。
今回は丁度、シネマイベント(5/19~20)とも重なったこともあり、賑わいをみせておりました。
2012年5月17日木曜日
筑波研究学園都市をみる
2012年5月6日日曜日
小田原中継所を見て (地域を活性するヒント)
2012年5月3日木曜日
佐原のまち
2012年4月25日水曜日
春の山形
2012年4月24日火曜日
感性のデザインを忘れずに!
空間をプランニングする、デザインする立場より思うこと。
都市をつくっていくこと、まちをつくっていくこと、地域をつくっていくことは、短絡的に単純にモノをつくる、こわすというだけのものではない。
人々の生活の舞台とは、いろんな要素が単純かつ複雑に絡み合っているもの。
良かれと思って事業を進めても、反発を喰らってしまう事もしばしばであります。
どうして、そんなことになってしまうのか。
その一因としては、業務やプロジェクトそのものだけしか見ようとしないことにあるような気がします。
仕事を進めていく上では、そのことに集中するのはとても大切なのですが、何かを忘れてしまってしまいがち。
空間の設計でいえば、空間の構成、構造を考えることはもちろんなのですが、その先の目標とされる人々の思いでの記憶に残るような空間づくりを念頭におき進めていくことが必要となります。
ある意味、自分たちの住むステージを創っていくことは、機能のデザインの他に、感性のデザインについても忘れてはなりません。
都市をつくっていくこと、まちをつくっていくこと、地域をつくっていくことは、短絡的に単純にモノをつくる、こわすというだけのものではない。
人々の生活の舞台とは、いろんな要素が単純かつ複雑に絡み合っているもの。
良かれと思って事業を進めても、反発を喰らってしまう事もしばしばであります。
どうして、そんなことになってしまうのか。
その一因としては、業務やプロジェクトそのものだけしか見ようとしないことにあるような気がします。
仕事を進めていく上では、そのことに集中するのはとても大切なのですが、何かを忘れてしまってしまいがち。
空間の設計でいえば、空間の構成、構造を考えることはもちろんなのですが、その先の目標とされる人々の思いでの記憶に残るような空間づくりを念頭におき進めていくことが必要となります。
ある意味、自分たちの住むステージを創っていくことは、機能のデザインの他に、感性のデザインについても忘れてはなりません。
2012年4月15日日曜日
2012年4月13日金曜日
うつのみやの夜桜
2012年4月10日火曜日
盛岡のまち
2012年4月6日金曜日
震災がれき(大谷石)の再利用
栃木県においても、昨年の東日本大震災では、大きな被害を被りました。
特に、栃木県北部、東部地域の揺れが大きく、お城の土塁(城壁など)の崩壊、地場材の大谷石を使った蔵や塀がことごとく崩れてしまっている状況です。
【大谷石(がれき)の活用について】
大谷石は凝灰岩であり、栃木県宇都宮市の大谷地区を中心に採掘できる石として 全国的にも有名な石であります。
凝灰岩でもあり、強度的には比較的弱いのが大谷石。
最近は、石の加工技術も進み、かつ石の風合いは もともといいものですから 建築の壁材のパネルなどに使われていたりします。
宇都宮などでは、ショッピングセンターなどの化粧壁材としてつかわれていたりし、地場材の活用とともつながり、宇都宮、栃木らしさを演出しております。
特に、栃木県北部、東部地域の揺れが大きく、お城の土塁(城壁など)の崩壊、地場材の大谷石を使った蔵や塀がことごとく崩れてしまっている状況です。
【大谷石(がれき)の活用について】
大谷石は凝灰岩であり、栃木県宇都宮市の大谷地区を中心に採掘できる石として 全国的にも有名な石であります。
凝灰岩でもあり、強度的には比較的弱いのが大谷石。
最近は、石の加工技術も進み、かつ石の風合いは もともといいものですから 建築の壁材のパネルなどに使われていたりします。
宇都宮などでは、ショッピングセンターなどの化粧壁材としてつかわれていたりし、地場材の活用とともつながり、宇都宮、栃木らしさを演出しております。
2012年4月4日水曜日
「空間をつくるしごと」をしていくための心得
人々が行き交う、憩う空間をつくっていく仕事、自然風景を創出していく仕事...などなど。
それは、「ランドスケープデザイン」分野の仕事 とも言われています。
通常の規格モノの設計と違い(もちろん基準、きまりはありますが)、創造性を盛り込んだ仕事の領域であります。
残念なのが、基準、きまりはこうだからこの形しか出来ないと決め付けてしまっていること。
以前も同じようなことを述べましたが、基準の先にあるものを抑えながら、その基準をどのように活用していくかという考えにシフトしていかなければなりません。
それは、「ランドスケープデザイン」分野の仕事 とも言われています。
通常の規格モノの設計と違い(もちろん基準、きまりはありますが)、創造性を盛り込んだ仕事の領域であります。
残念なのが、基準、きまりはこうだからこの形しか出来ないと決め付けてしまっていること。
以前も同じようなことを述べましたが、基準の先にあるものを抑えながら、その基準をどのように活用していくかという考えにシフトしていかなければなりません。
2012年4月3日火曜日
設計のしごと
設計のしごと。(地方都市において、ランドスケープ領域の仕事を考えた場合)
設計のしごとを全般的に見ると、
「時には、指示をして仕事を統括し、全体を見なくてはいけないときもあれば、
その一方では、部分的なパーテンションの中で強い歯車としても動かなくてはいけない。」
両面性を持ち合わせることが必要な仕事(領域)です。
新卒間際のフレッシュマンの時期は、いきなり最初からは頭(指示側)になって動くことは困難に近い状況です。
設計のしごとを全般的に見ると、
「時には、指示をして仕事を統括し、全体を見なくてはいけないときもあれば、
その一方では、部分的なパーテンションの中で強い歯車としても動かなくてはいけない。」
両面性を持ち合わせることが必要な仕事(領域)です。
新卒間際のフレッシュマンの時期は、いきなり最初からは頭(指示側)になって動くことは困難に近い状況です。
2012年4月2日月曜日
時代はどんどん進んでいくもの
日々の仕事や生活の中で感じることとして、世の中の進行のスピードが速くなっているなぁと思うことが多々あります。
情報化社会の発展の中、日々の業務も以前よりもスピードを要求され、迅速な対応が求められております。
スピードに対応すること、要望に応える事はとても大切なことです。
その一方で、置き去りにされてしまっているものもあります。
情報化社会の発展の中、日々の業務も以前よりもスピードを要求され、迅速な対応が求められております。
スピードに対応すること、要望に応える事はとても大切なことです。
その一方で、置き去りにされてしまっているものもあります。
2012年3月30日金曜日
仕事でチームを組むということは
設計の仕事においてチームを組むということは、お互いの作業量を均等化することや、それぞれの専門分野の技術を束ねることによって、より精度の高い設計を仕上げていくことを目指して人をまとめ、作業を分業したりします。
本来は仕事を効率化し、よりよい成果品をつくるためのチームづくりが目的とされますが、これらのことが一部的に悪用されてしまうケースもあります。
こんなことになったら、要注意!
本来は仕事を効率化し、よりよい成果品をつくるためのチームづくりが目的とされますが、これらのことが一部的に悪用されてしまうケースもあります。
こんなことになったら、要注意!
2012年3月29日木曜日
後の世代のことを見据えて...欲しい。
先人たちが築いてきたこと、自分の世代がすべきこと。
激動の世の中の真っ只中である、日本においてやっていかなくてはいけないこととは何であるか?
→ 少子高齢化社会、高齢者社会へ対応させるための仕組みづくり
→ 子供の世代、孫の世代が生活を成り立たせるようにしていくための仕組みづくり
→ 高齢になったときに生きがいを感じられる仕組みづくり
他にもやるべきことは沢山あるでしょう。
考えれば、考えるほどたくさんのやらなければいけないことが頭の中をよぎります。
激動の世の中の真っ只中である、日本においてやっていかなくてはいけないこととは何であるか?
→ 少子高齢化社会、高齢者社会へ対応させるための仕組みづくり
→ 子供の世代、孫の世代が生活を成り立たせるようにしていくための仕組みづくり
→ 高齢になったときに生きがいを感じられる仕組みづくり
他にもやるべきことは沢山あるでしょう。
考えれば、考えるほどたくさんのやらなければいけないことが頭の中をよぎります。
2012年3月28日水曜日
まちあるき から見えるモノ、学ぶコト
いろんな地方の中心市街地や地域集落。
それぞれの風景やまちなみ、そして文化と人々のふれあいが、それぞれの空間の魅力となっております。
自分たちが生活しているまちについて、どのように向き合っていくか。
いろんな考え方があると思います。
空間の設計をしている身としては、建物や路地空間の構成や樹木の配置、見え方などランドスケープ的に形を捉えることを自然と体で感じ取っているような感じです。
それぞれの風景やまちなみ、そして文化と人々のふれあいが、それぞれの空間の魅力となっております。
自分たちが生活しているまちについて、どのように向き合っていくか。
いろんな考え方があると思います。
空間の設計をしている身としては、建物や路地空間の構成や樹木の配置、見え方などランドスケープ的に形を捉えることを自然と体で感じ取っているような感じです。
登録:
投稿 (Atom)